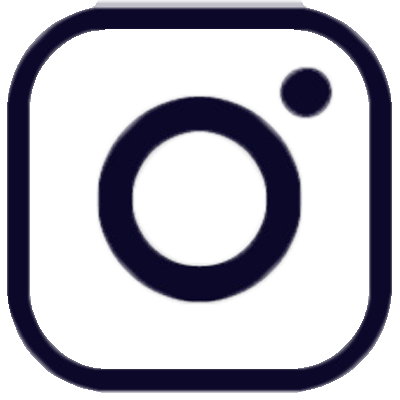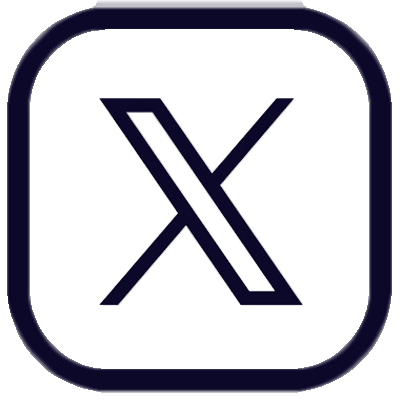お役立ち情報
2025.04.28
保健師学校の入試で出た小論文のお題(10)『共働きの一般化(800字)』

保健師学校の入試で出た小論文のお題(10)
⁻『共働きの一般化(800字)』
近年、日本では「共働き」が当たり前の時代になってきました。かつては男性が働き、女性は家庭を守るというスタイルが一般的でしたが、社会構造や人々の意識の変化により、今や共働き世帯が多数派となっています。
今回は、共働きの現状や背景、メリット・デメリット、そして今後の社会の動向について考察し、保健師学校の小論文対策にも役立つような内容をまとめます。
| ●共働きの現状 |
まず、日本における共働き世帯の現状について見てみましょう。
厚生労働省「国民生活基礎調査」(令和4年版)によると、共働き世帯の割合は年々増加しており、2022年時点で約68%に達しています。これは、専業主婦世帯(約32%)の2倍以上の数字です。 また、1980年には共働き世帯は全体の約36%だったことを考えると、この40年間で大きな変化があったことがわかります。
年代別では、20代・30代の若い世代で共働きが一般的になっている一方、50代以上でも共働きを選択する家庭が増えています。
背景には、子どもの教育費や住宅ローン返済、老後資金の確保といった経済的理由が大きく関係しています。
| ●なぜ共働きが増えているのか |
共働き世帯が増加している要因には、いくつかの社会的背景が挙げられます。
まず、男女雇用機会均等法(1986年施行)により、女性の社会進出が推進されたことが大きな転機となりました。その後も「働き方改革」や育児休業制度の整備などにより、女性が仕事と家庭を両立しやすい環境が徐々に整備されてきました。
さらに、日本人の意識も大きく変化しています。かつては「結婚=退職」が当然とされていた時代もありましたが、今は「結婚しても働き続ける」「子育てと両立しながら働く」ことが自然と受け入れられるようになっています。 高齢出産が増加している現代においては、子育てと仕事を並行して行う必要があり、なおさら共働きが一般化しているのです。
経済的な要因も無視できません。1人分の収入だけでは生活が難しい家庭が増え、共働きによる安定収入を求める傾向が強まっています。
| ●共働きのメリットとデメリット |
【メリット】
・経済的安定:収入が2本立てとなるため、生活の安定が図れる。
・女性の自己実現:家庭以外にも社会で活躍できる場が広がる。
・子どもの教育環境:経済的な余裕があるため、習い事や教育費に充てることができる。
【デメリット】
・家事・育児負担の増大:仕事と家庭の両立によるストレスが発生しやすい。
・子どもへの影響:親が忙しく、子どもとのコミュニケーションが減ることも。
・時間的制約:自分自身の時間やリフレッシュの時間が少なくなる。
特に医療職を目指す人にとっては、共働き生活の中でも、シフト勤務や夜勤があるため、家族のサポート体制が不可欠です。 「家族に支えられて働く」という意識が大切になります。
| ●今後の展望 |
これからの日本社会では、共働きはますます一般的になり、単なる選択肢ではなく「標準」となるでしょう。 「働き方改革」の流れを受けて、テレワークやフレックスタイム制の導入も進んでおり、家庭と仕事を両立しやすい環境が整いつつあります。
また、医療職の現場でも共働きを前提とした職場環境づくりが求められています。 例えば、短時間勤務制度、院内保育所の設置、急な子どもの病気に対応できる休暇制度などが充実しつつあります。 特に保健師は地域活動や学校保健に関わることも多く、柔軟な働き方が求められる場面も多い職種です。 これからの医療職には、「仕事も家庭もあきらめない」というバランス感覚がますます重要になるでしょう。
| ●小論文・作文の書き方のヒント |
このテーマで小論文や作文を書くときは、次のポイントを押さえましょう。
・冒頭で「共働きの現状」を簡単にまとめる
・なぜ増えているのかの背景を説明する(社会変化、意識の変化)
・メリット・デメリットをバランスよく書く
・今後について自分の意見を述べる
・医療職との関連を少し触れると、専門性が出る
「一方的に共働きを肯定する」だけでなく、「課題もある」という視点を持って書くと、より深みのある内容になります。
| ●まとめ |
共働きの一般化は、日本社会の大きな流れのひとつです。経済的な理由だけでなく、個人の生き方の多様化、社会制度の整備など、さまざまな要因が絡み合っています。 これからの社会では、共働きが前提となったライフスタイルがますます増えていくでしょう。
医療職として働く中でも、患者さんや家族の共働き事情に配慮する場面は増えていきます。保健師を目指す皆さんには、自らの働き方にも向き合いながら、支援する側としての視点を持っていてほしいと思います。
お問い合わせ
Contact
看護予備校、准看護予備校を選ぶなら京都・大阪・滋賀・兵庫から通いやすいアルファゼミナール