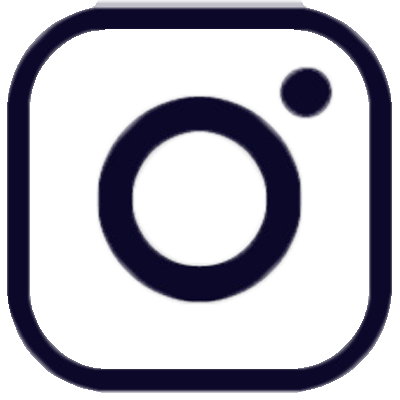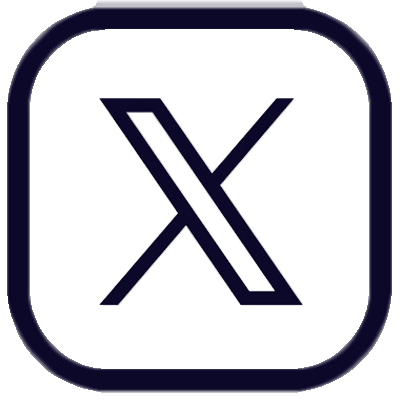お役立ち情報
2025.04.23
助産学校の入試で出た小論文のお題(10)『出生前診断の必要性について(800字)』
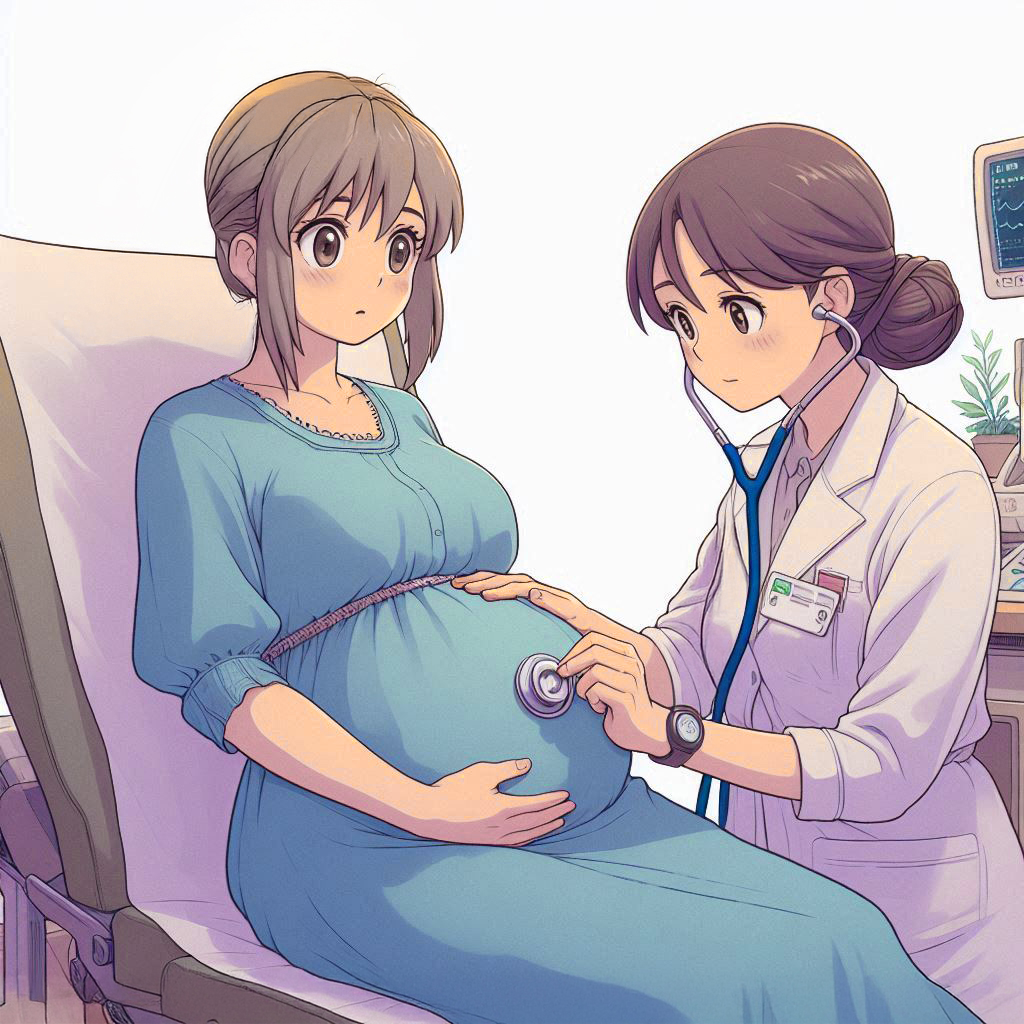
助産学校の入試で出た小論文のお題(10)
⁻『出生前診断の必要性について』
助産学校の小論文で「出生前診断(出産前診断)の必要性について」というお題が出されたことがあります。これは医療の進歩と共に、出産を取り巻く環境が大きく変化している今、助産師を目指す受験生にとって避けては通れないテーマです。
本記事では、出産前診断とは何か、メリットと課題、そして助産師としての姿勢について、整理しながら考えていきましょう。
| ●出産前診断とは何か |
出生前診断(出産前診断)とは、赤ちゃんが生まれる前に胎児の健康状態や遺伝的な疾患の有無などを調べる医療行為です。代表的な検査としては、超音波検査や母体血清マーカー検査、羊水検査、NIPT(新型出生前診断)などがあります。
これらの検査を通じて、ダウン症候群や18トリソミーなどの染色体異常、心疾患や臓器の異常などの可能性を早期に知ることができます。
| ●メリットと課題 |
出生前診断を受けるメリットとしては、以下のような点が挙げられます。
・早期に準備を始められる(医療体制・生活環境の整備)
・出産後の子どもへの医療対応がスムーズになる
・精神的な覚悟や受け入れができる時間ができる
しかし、同時に重要な課題もあります。
・検査結果によって妊娠の継続に悩むことになる
・選択のプレッシャー(生むか・中絶するかという葛藤)
・偽陽性・偽陰性のリスクがある
・「命を選別すること」への倫理的な問い
出産前診断には、高い精度や情報の透明性が求められる一方で、それをどのように受け止めるかは人それぞれであり、一つの「正解」がないのが現実です。
| ● 認知度と実際の受診状況 |
最近ではSNSやメディアで「NIPT」という言葉が知られるようになり、出生前診断の認知度は高まってきました。しかし、実際に検査を受ける人の割合はそこまで多くはありません。費用の高さ、情報の不足、結果に対する不安などが要因として挙げられます。
また、受診者は高齢出産や遺伝的疾患の家族歴がある人に限られる傾向があります。
| ●助産師としてのスタンス |
このテーマにおいて、助産師を志す受験生が大切にしたいのは「中立な立場で支える姿勢」です。
出産前診断は、未来の不安を減らす一助になる一方で、「診断を受けること自体が正解」というわけではありません。
診断を受けるか否か、その結果をどう受け止めるか――これはご夫婦にとって非常に繊細な選択です。助産師としては、どんな選択も尊重し、正解のない問いに対して、「あなたの選んだ道でいいんですよ」と温かく寄り添える存在であるべきです。
出産前診断は、家族が将来の生活や幸せを見つめ直すきっかけにもなります。しかし、それを必要とするかどうかは一人ひとり異なります。だからこそ私は、診断を受けるか否か、どんな結果を受け入れるかという難しい選択に直面した夫婦の心に寄り添い、それぞれの決断を温かく支えられる助産師でありたいと考えています。
| ●まとめ |
「出産前診断の必要性について」というお題では、賛成・反対どちらの立場でも書くことは可能です。しかし重要なのは、単なる医学的知識を並べるのではなく、「命をめぐる選択に立ち会う助産師」として、どんな姿勢でその選択に向き合いたいかを表現することです。
出産前診断はこれからますます身近な選択肢になります。その一方で、悩み苦しむご家族も増えるでしょう。だからこそ「支える立場」である助産師の存在が、今後いっそう大切になっていくはずです。
お問い合わせ
Contact
看護予備校、准看護予備校を選ぶなら京都・大阪・滋賀・兵庫から通いやすいアルファゼミナール