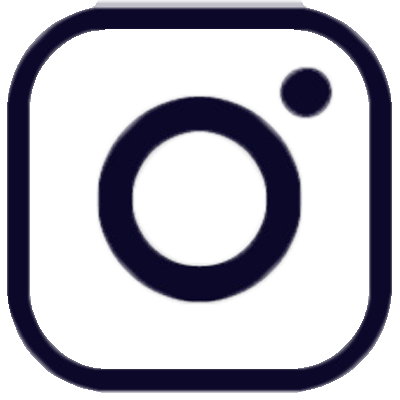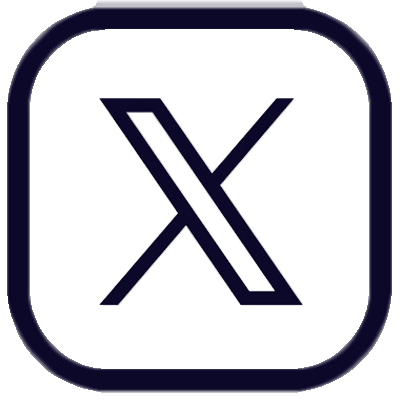お役立ち情報
2025.04.22
看護大学・看護学校の入試で出た小論文・作文のお題(17)『方言で話すことについてあなたの考えを具体例を挙げながら論じなさい。(800字)』

看護学校の入試で出た小論文・作文のお題(17)
⁻『方言で話すことについてあなたの考えを具体例を挙げながら論じなさい。(800字)』
看護大学や看護学校の入試では、受験生の価値観や視野の広さ、対人関係の感受性などが試されるお題が多く出されます。「方言で話すこと」についての小論文もそのひとつ。 このテーマは単なる言葉遣いの話にとどまらず、コミュニケーションの本質や、地域性・文化への理解、さらには医療者としての接し方にも関わる重要な論点を含んでいます。
この記事では、方言をテーマとした小論文を書くために意識したい視点や構成、具体的な論点を丁寧に紹介します。
| ●方言で話すことのメリット・デメリット |
まずは、方言の持つ特徴について考えてみましょう。
言の最大のメリットは、「親しみやすさ」「温かみ」「距離の近さ」を感じさせることです。特に医療・看護の場面において、患者さんに安心感を与えるという点で大きな役割を果たします。例えば、病院のベッドで緊張している高齢の患者さんに、看護師がその土地の方言で「無理せんでね」と声をかけると、患者さんの顔がほっとゆるむことがあります。
一方で、方言には「通じにくさ」や「誤解を生むおそれ」があることも事実です。特に多職種との連携や医療ミスのリスクを考えると、標準語での明確な表現が求められる場面も少なくありません。
| ●医療現場でのTPOと方言の使い分け |
方言を使うべきか否か。
それは「TPO(時と場所、場合)」によって異なります。たとえば、患者さんとの雑談や安心させるための声かけには方言が有効でも、カルテ記入や申し送り、医師とのカンファレンスでは標準語で明確に伝える必要があります。 さらに、患者さんの出身地にも配慮が必要です。
たとえば、遠方から入院してきた患者さんにその地域の濃い方言で話しかけても、かえって不安にさせてしまうことがあります。そのようなときには「相手に合わせて言葉を選ぶ力」が重要です。
| ●方言と医療者の「信頼関係」づくり |
方言は、その土地で育った人の文化でありアイデンティティです。その地域に長く住んでいる人にとっては、方言で話しかけられることで「この人は自分たちのことを理解してくれている」という安心感や信頼感が生まれます。
たとえば、訪問看護の現場では、看護師が地域に溶け込み、地域の人たちと心を通わせるために、あえて方言を覚えて使っているというケースもあります。赴任地への愛着や地域住民へのリスペクトを示す意味でも、方言は「通じる医療」のツールになると言えるでしょう。
| ●方言・敬語・医療者としての言葉遣い |
医療の場では「丁寧さ」「わかりやすさ」「正確さ」が求められます。そのため、方言を使う際にも敬語とのバランスを考える必要があります。 方言は親しみがある一方、フォーマルな場では不適切とされることもあります。
小論文では、こうした「使い分けの意識」や「相手に配慮した言葉選び」ができることを示すと、読み手に好印象を与えることができます。 また、近年では「子どもが親の方言を受け継がず、標準語だけを話すようになる」ことへの懸念もあります。文化の継承という観点からも、方言に対する理解と尊重は大切な姿勢です。
| ●小論文を書く際のポイント |
このお題では、単に「方言はいい/悪い」と述べるのではなく、「どう使い分けるか」「自分ならどう考えるか」「看護師としてどう生かしたいか」という視点が求められます。
【書きやすい構成の一例】
はじめに:テーマの提示(例:近年、方言が見直されている。医療の現場でも…)
本論①:方言のメリットと医療現場での活用例
本論②:方言の注意点と使い分けの大切さ
本論③:自分の体験や考え(例:祖父母との会話、病院実習での経験)
まとめ:看護師として、相手に寄り添う言葉選びを心がけたい
| ●まとめ:言葉の選び方は「思いやり」のあらわれ |
看護の仕事は「人」に寄り添う仕事です。言葉はそのための大切な道具。方言という地域のぬくもりある言葉を、相手や場面に合わせて上手に使える看護師は、それだけで信頼を得ることができるはずです。
このテーマは、単に「方言」について語るのではなく、「どう人と関わるか」「どんな看護師になりたいか」を伝える良いチャンス。 ぜひ、あなたらしい視点を織り交ぜて書いてみてください。
お問い合わせ
Contact
看護予備校、准看護予備校を選ぶなら京都・大阪・滋賀・兵庫から通いやすいアルファゼミナール