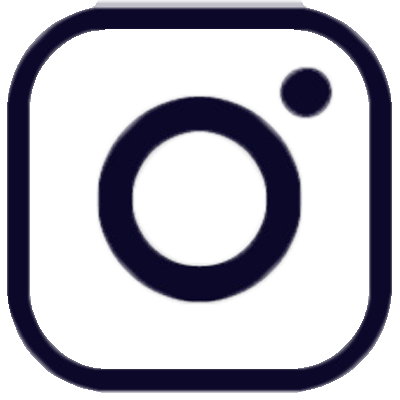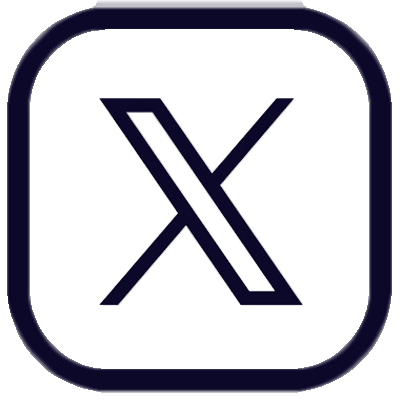お役立ち情報
2025.04.22
保健師学校の入試で出た小論文のお題(8)『共食と孤食について(800字・60分)』
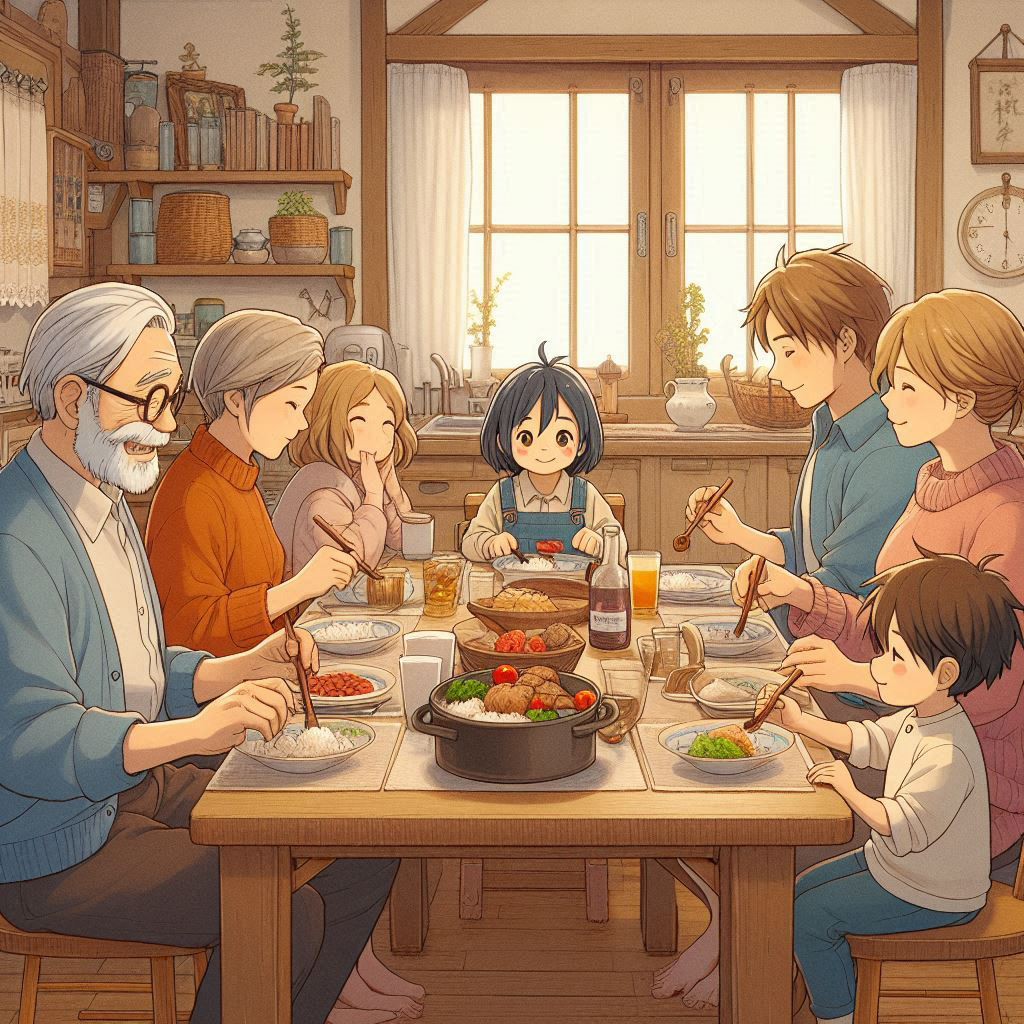
保健師学校の入試で出た小論文のお題(8)
⁻『共食と孤食について(800字・60分)』
保健師学校の小論文試験では、「共食と孤食」など、身近でありながらも社会性の高いテーマが出題されることがあります。一見すると答えやすそうなテーマに思えるかもしれませんが、求められているのは、自分自身の経験や価値観、医療職としての視点をふまえて深く考える力です。
この記事では、「共食と孤食とは何か」という基本から、現代社会の課題、保健師としての立場での考え方まで、小論文に盛り込みたいポイントをわかりやすくまとめていきます。
| ●共食と孤食とは? |
まずは用語の意味を確認しておきましょう。
共食(きょうしょく):家族や友人、職場の同僚など、誰かと一緒に食事をすること。
孤食(こしょく):ひとりで食事をすること。
さらに派生語として、
個食:同じ空間にいながら別々のものを食べること。
子食:子どもだけで食べること。
固食:同じものばかり食べること。
といった言葉もあります。
これらの言葉には、食生活が多様化し、家庭の在り方や生活習慣が変化している現代社会の背景が反映されています。
| ●孤食の現状とその原因 |
孤食が増加している背景には、次のような理由が考えられます。
・高齢者の一人暮らしの増加
・仕事による帰宅時間の不規則化
・子どもたちの習いごと・塾・部活動
・核家族化・共働きの家庭の増加
・コロナ禍での外食・会食の制限
こうした状況の中で、1日3食すべてをひとりで食べる人も珍しくありません。
孤食には「自分のペースで自由に食べられる」「誰にも気を遣わずに済む」といった利点もありますが、次のようなデメリットも存在します。
・栄養バランスが偏りやすい
・食生活が不規則になりやすい
・会話がないことによる孤独感の増大
・精神的な健康状態の悪化(うつ傾向、意欲低下)
・フレイル(虚弱)の進行や認知機能の低下につながる可能性
とくに高齢者においては、孤食が身体的・精神的健康の悪化をもたらすことが多く、保健師による地域支援や食支援の必要性が高まっています。
| ●共食がもたらすメリットとは? |
一方の「共食」には、次のようなプラスの効果が期待できます。
・会話のきっかけとなる → 家族間の信頼関係の構築
・子どもの食育の場 → 食べ方・栄養バランス・マナーの習得
・高齢者の生きがいにつながる
・規則正しい生活リズムの形成
・他人と食卓を囲むことで社会性や安心感が得られる
また、共食を通じて「今日はどうだった?」「最近ちょっと元気ないね」など、家族や仲間同士のささいな気づきが病気の早期発見やメンタルケアにつながることもあります。
ただし、共食にも課題はあります。家庭内に緊張感があったり、話題がない、スマホばかり見ているといった場合は、かえって苦痛になることもあります。単に「一緒に食べる」だけではなく、「楽しい時間になる工夫」も求められています。
| ●今後の食習慣と保健師としての視点 |
現代はライフスタイルが多様化し、「1人の時間が大切」「無理に合わせて食べたくない」という価値観もあります。その中で、共食と孤食のどちらが良いかを一概に決めるのではなく、「どんな食生活がその人にとって健康的で豊かなのか」を考える視点が必要です。 保健師や看護職は、地域住民の健康を支える立場として、こうした個々の背景や価値観を尊重しつつ、以下のようなサポートを考えていくことが求められます。
・地域の食事支援活動(配食、食事会など)への関与
・栄養相談や食生活の見直し支援
・生活リズムや孤独への支援を含めた包括的な健康支援
また、学校現場でも、家庭の事情で孤食をしている子どもへの気配り、給食の時間を大切にする工夫、地域とのつながりを持った食育活動など、共食の機会を増やす取り組みが期待されています。
| ●小論文で伝えたい「あなたの健康観」 |
このテーマでは、「あなたはどんな食生活を送っているのか」「その中で何を感じ、何を工夫しているか」を言葉にすることが大切です。たとえば…
「一人暮らしなので孤食が多いが、栄養バランスを意識し、決まった時間に食事を取るようにしている」
「実家にいた頃は共食のありがたさに気づかなかったが、離れて初めてその大切さを感じた」
「保健師として、人とのつながりを大切にした支援ができるようになりたい」
このように、自分の体験をふまえた考察や、将来への思いを述べると、小論文として説得力のある内容になります。
| ●まとめ:食卓には、健康とつながりが宿る |
共食と孤食は、単なる「食べ方」の話ではなく、人と人との関わり方、社会とのつながり、そして健康な暮らし全体に関わるテーマです。
小論文を書く際は、「知識」だけでなく、「自分自身の経験や思い」「医療職としての視点」を組み合わせ、深みのある文章に仕上げていきましょう。
お問い合わせ
Contact
看護予備校、准看護予備校を選ぶなら京都・大阪・滋賀・兵庫から通いやすいアルファゼミナール