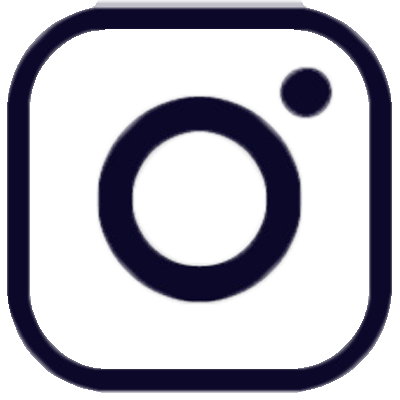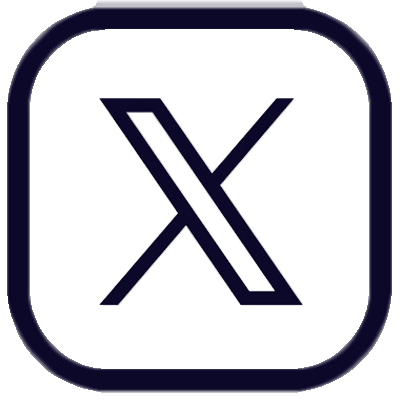お役立ち情報
2025.04.21
看護大学・看護学校の入試のグループ討論で出されたお題(13)『歩きスマホについて』

看護大学・看護学校の入試のグループ討論で出されたお題(13)
⁻『歩きスマホについて』
グループ討論のテーマとして近年よく取り上げられる「歩きスマホ」。普段の生活の中でも、街中や駅のホームなどで、スマートフォンを操作しながら歩いている人を見かける機会は多いのではないでしょうか。 このお題では、スマホ依存やモラル、公共の安全など、現代社会が抱えるさまざまな課題が浮き彫りになります。
今回は、「歩きスマホ」をテーマにしたグループ討論の進め方やポイントを考えてみましょう。
| ●歩きスマホはなぜ問題なのか |
まず押さえておきたいのは、「歩きスマホがなぜ問題なのか」という視点です。 歩きながらスマートフォンを使うことで、周囲への注意力が大幅に下がり、他人との衝突や駅のホームからの転落、道路への飛び出しといった事故につながる可能性があります。 特に看護職をめざす受験生としては、「公共の場での危険性」や「周囲への配慮」に対する意識があるかどうかが問われていると考えましょう。
また、「歩きスマホ」に限らず、「ながらスマホ」(例:運転中・自転車に乗りながら・食事中など)も増えており、いずれも注意力の欠如や生活リズムの乱れにつながるといった健康面の影響も指摘されています。
| ●なぜ歩きスマホをしてしまうのか |
歩きスマホが問題視されながらも、なかなか減らないのはなぜでしょうか?
多くの人が「スマホの通知が気になる」「すぐに返信しなければならないと思ってしまう」「立ち止まる時間が惜しい」などの理由で歩きながら使ってしまうようです。 また、スマホの中にはSNS、チャット、地図アプリ、音楽など、生活のあらゆる機能が詰まっているため、つい依存的になってしまうという側面もあります。
「現代人の生活にスマホが深く入り込んでいること」を前提に考えると、現実的な対策が見えてくるかもしれません。
| ●どうすればやめられる?歩きスマホの防止策 |
討論では、「ではどうすれば歩きスマホを減らせるか?」という建設的な方向に話を持っていくとよいでしょう。
たとえば:
・駅構内や繁華街での注意喚起ポスターやアナウンスの強化
・スマホ側の機能制限(歩行中は画面操作をロックする機能など)
・学校教育や啓発イベントを通じたモラル教育
・個人レベルでは「必ず立ち止まって操作する」などのルールづくり
また、「歩きスマホは現代の“歩きたばこ”のようなものだ」という意見もあります。かつては歩きながらの喫煙が当たり前でしたが、今ではマナー違反として社会全体が意識を変えました。 このように、社会全体の価値観やモラルが変わることで、「歩きスマホ」も抑制される可能性があるでしょう。
| ●グループ討論の進め方とポイント |
このような生活に身近なテーマの討論では、「正論だけで終わらせない」のがポイントです。
たとえば、ある人が「絶対にやめるべきだ!」と強く言っても、別の人が「でも私もつい、地図アプリを見ながら歩いちゃう」と言えば、そこからリアルな議論が生まれます。
また、「自分自身の体験」や「見たことのある具体例」を挙げると、討論の場に説得力が生まれます。さらに、討論の最後には「私たちはこう考えました」とグループの結論や提案を簡潔にまとめることも忘れずに。
| ●まとめ |
「歩きスマホ」は現代社会の象徴ともいえるテーマです。便利さの裏にあるリスクにどう向き合うか、モラルと利便性のバランスをどうとるか――医療職をめざす者として、公共の安全に敏感であることはとても大切です。
グループ討論では、自分の意見をしっかり持ちつつも、他人の意見に耳を傾けて柔軟に議論を進める姿勢が求められます。日常の中の小さな問題にも、自分なりの視点を持って臨んでいきましょう。
お問い合わせ
Contact
看護予備校、准看護予備校を選ぶなら京都・大阪・滋賀・兵庫から通いやすいアルファゼミナール