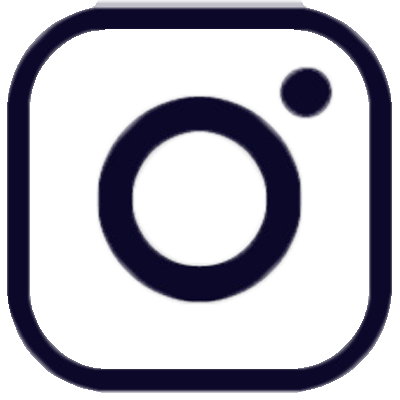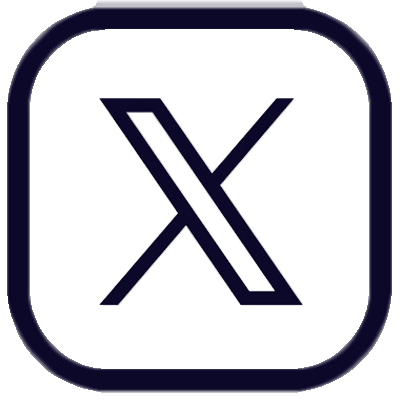お役立ち情報
2025.04.16
助産学校の入試で出た小論文のお題(9)『きょうだい児について(800字)』

助産学校の入試で出た小論文のお題(9)
⁻『きょうだい児について(800字)』
近年、医療や福祉の現場において「きょうだい児」という言葉が注目されています。助産学校や保健師学校の小論文でも取り上げられるこのテーマは、命を支える助産師を目指す上で、子どもとその家族の「まるごと」に寄り添う視点が求められていることを意味しています。
今回は「きょうだい児」というテーマについて、どのように小論文に取り組めばよいかを解説していきます。
| ●きょうだい児とは |
「きょうだい児」とは、障がいや病気を持つ兄弟姉妹がいる健常な子どものことを指します。
たとえば医療的ケア児、障害を持つ子などの兄弟姉妹が、家族の中で“支える側”として生きる中で、心に負担を抱えることがあるのです。 きょうだい児自身は体に不調があるわけではないため、支援の網からこぼれやすく、その存在が見過ごされがちです。
ですが、彼ら彼女らの「我慢」や「遠慮」は、長い時間をかけて心の負担として積み重なっていくことがあります。
| ●きょうだい児が抱える課題とその背景 |
きょうだい児は幼少期から、親が病気や障がいを持つ兄弟姉妹の世話や通院に忙しい様子を見て、「自分は迷惑をかけてはいけない」「いい子でいなきゃ」と無意識に思い込んでしまうことがあります。
特に多いのは、以下のような状況です。
過度な期待や役割の押しつけ:「お兄ちゃん(お姉ちゃん)の分もがんばろうね」と言われ、自分の感情や欲求を後回しにする
孤独感や劣等感:病気のきょうだいにばかり親の目が向いていると感じ、自分は必要とされていないと思い込む
将来への不安:きょうだいの将来の介護や支援を自分が担うのではないかという不安
また、経済的な制約や家庭環境の影響で、自分の夢や進学をあきらめる選択をせざるを得ないケースも少なくありません。
| ●支援と理解を広げるには |
きょうだい児への理解と支援の輪を広げるためには、社会全体がこの存在に目を向けることが必要です。保健師や助産師としてできることもあります。
地域での支援グループの設置:きょうだい児同士が気持ちを共有できる居場所や、リフレッシュの場を提供すること
保護者への声かけ:「この子(健常児)もがんばってるんですね」と、きょうだい児へのまなざしを家庭にも届ける
学校や地域への啓発:先生や地域の大人がきょうだい児の存在を知り、見守る意識をもつことが大切です
また、福祉や医療、保育の場で「きょうだい児」という概念が当たり前のように共有されることで、見えにくい心のケアが届きやすくなります。
| ●小論文を書く際のポイント |
このテーマに取り組む際は、「きょうだい児とは誰か」「どのような現状があるのか」を明確にし、自分の意見や提案につなげることが大切です。
例えば、
・自分のまわりにも似た経験をした子がいたこと
・保健師として、家庭全体に目を向けることの必要性
・子どもたち一人ひとりが大切にされる社会への願い
などを軸にすると、説得力のある文章になります。具体例を挙げるとリアリティが増しますし、「ただの問題提起」で終わらず、「だから私はこう考える」という結論をはっきり述べると印象が良くなります。
| ●まとめ |
きょうだい児は、目には見えない葛藤や苦労を抱えながら、健気に毎日を生きている子どもたちです。助産師や保健師を目指す私たちは、子どもや家族の“目に見えない部分”に寄り添える存在でありたいものです。
このテーマは、福祉や家族支援についての理解だけでなく、あなたの「人を見るまなざし」や「支援者としての姿勢」も問われています。丁寧に向き合い、自分の言葉でしっかりと書いていきましょう。
お問い合わせ
Contact
看護予備校、准看護予備校を選ぶなら京都・大阪・滋賀・兵庫から通いやすいアルファゼミナール