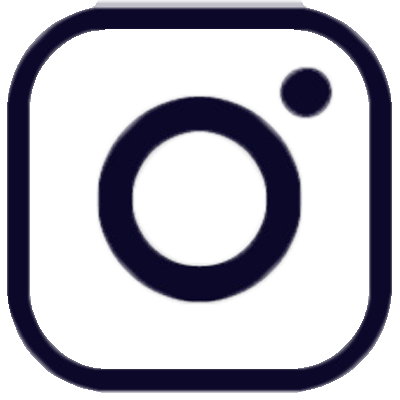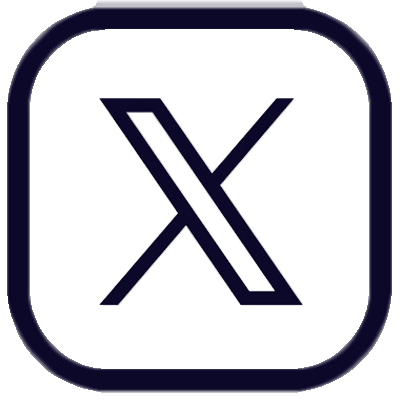お役立ち情報
2025.04.11
助産学校の入試で出た小論文のお題(7)『産後ケアの大切さについて(800字)』
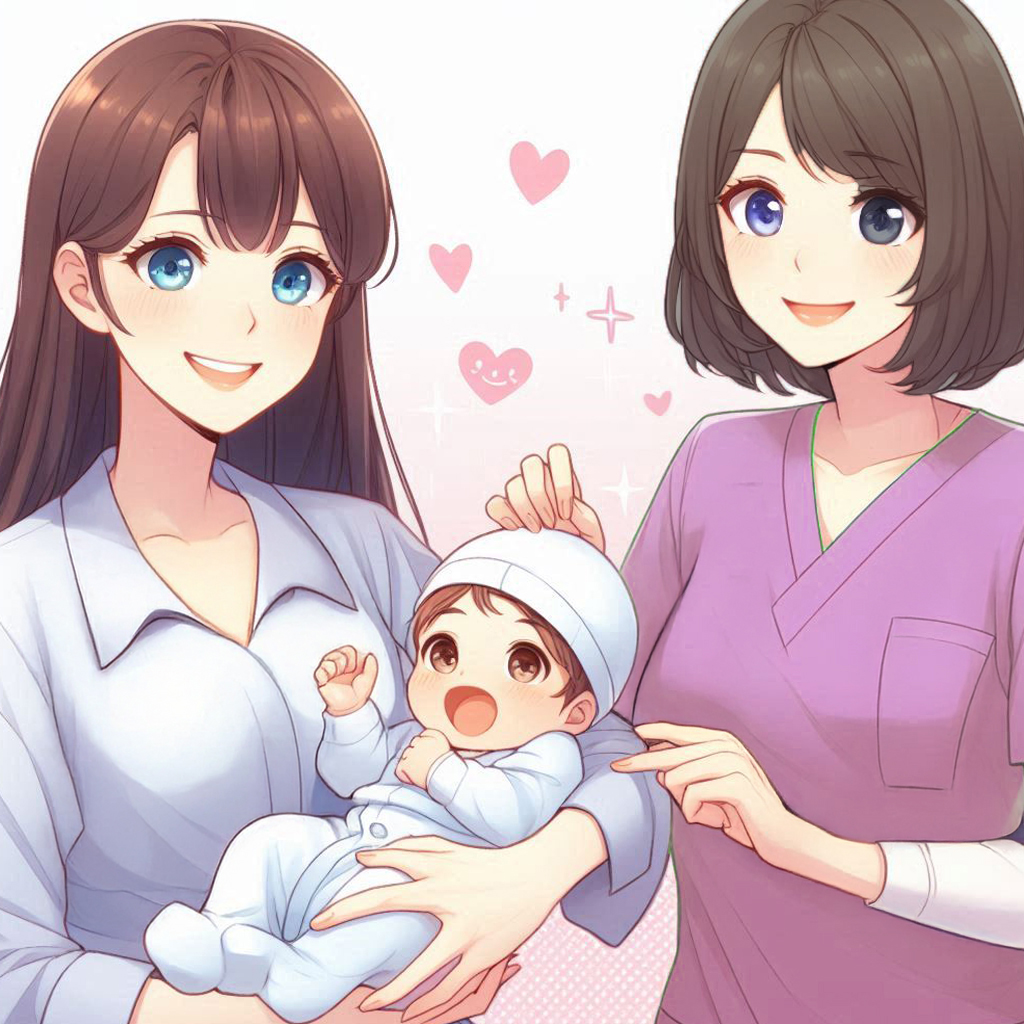
助産学校の入試で出た小論文のお題(7)
⁻『産後ケアの大切さについて(800字)』
近年、出産後の母親の心身の不調や育児不安が社会問題となっており、「産後ケア」の必要性が大きく叫ばれています。助産学校の小論文試験でも、「産後ケアの大切さ」について考える力が問われることがあります。
今回の記事では、このテーマについてどのように論じていくか、構成のポイントや最近のトレンドも交えながら考えていきます。
| ●産後ケアとは何か?~現代の背景をふまえて~ |
出産を終えた女性は、身体の回復とともに、ホルモンバランスの変化や育児に対する不安など、多くの負担を抱えることになります。家族や地域とのつながりが薄れがちな現代では、かつてのように周囲にサポートしてくれる人がいないまま孤独に育児をしているケースも増えています。
また、核家族化・共働き世帯の増加・高齢出産の増加など、現代ならではの要因が重なり、産後うつや虐待のリスクも指摘されています。こうした中で注目されているのが「産後ケア」の必要性です。
| ●なぜこのテーマが今、問われるのか? |
助産師の役割は「出産のサポート」に留まりません。妊娠中から出産、そして産後まで母子を継続して支える「継続ケア」が求められています。特に産後は、育児に不安を抱える母親が「誰かに話を聞いてもらえること」「安心できる場に身を置けること」が大きな支えになります。
そのため、助産師が産後ケアの現場において果たせる役割は多く、近年では自治体の「産後ケア事業」の拡充や、助産師が運営する「産後ケア施設」も増えてきました。こうした社会的背景があるからこそ、入試でこのテーマが出題されるのです。
| ●どんな内容を書けばよい?小論文構成のポイント |
小論文では、以下のような流れで構成すると書きやすくなります。
導入:「現代の母親が抱える産後の問題」について触れ、問題提起。
展開:「産後ケア」の意義、母親にとってのメリット、地域や医療との関係などを記述。
助産師としての視点:「どのように産後の母親を支えていきたいか」など、自分の将来像を重ねる。
結論:「産後ケアの重要性を多くの人に伝え、支援体制を広げていきたい」といった前向きなまとめ。
また、最近の情報として、産後ケアにかかわる自治体の支援制度(例:宿泊型・訪問型・デイケア型など)や、令和の産後うつの発症率などに触れても説得力が増します。
| ●どうしても書きづらいときは? |
もし具体的な事例が思い浮かばない場合は、自分のまわりの子育て中の家族・知人から聞いた話を参考にしたり、地域の子育て支援センターの取り組みを調べてみたりすると、書きやすくなります。
また、医療職として支援の目線に立つだけでなく、「1人の市民として、産後の母親をどう支える社会を作るか?」という広い視点でも書けると好印象です。
| ●まとめ |
「産後ケアの大切さ」というお題は、一見シンプルに見えて、現代社会や家族の在り方、地域支援や医療制度など、様々な背景が問われています。助産師を目指す受験生にとっては、産後の母親と赤ちゃんをどう支えていきたいか、自分の志とも深くつながるテーマです。
小論文では知識を問われるというよりも、「あなたはどう考えるか」「どう行動しようとしているか」が見られます。
丁寧に向き合って、あなたらしい答えを探してみてくださいね。
お問い合わせ
Contact
看護予備校、准看護予備校を選ぶなら京都・大阪・滋賀・兵庫から通いやすいアルファゼミナール