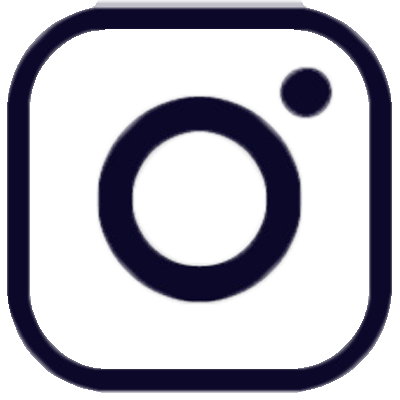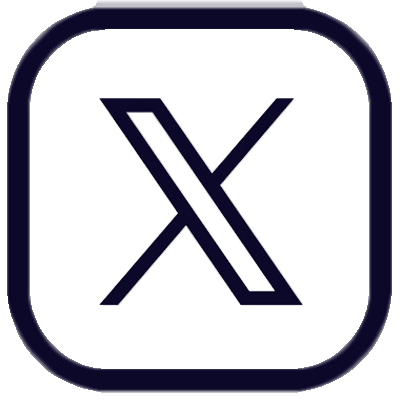お役立ち情報
2025.04.10
保健師学校の入試で出た小論文のお題(4)『現在の子どもは夜型化しているがそれはなぜか。また、それを防ぐためにはどのような対処方法があるか。(800字・60分)』

保健師学校の入試で出た小論文のお題(4)
⁻『現在の子どもは夜型化しているがそれはなぜか。また、それを防ぐためにはどのような対処方法があるか。(800字・60分)』
最近の子どもたち、夜更かししている印象がありませんか?
「なんだか昔より寝るのが遅い気がする…」「朝がつらそう」――そんな声が保護者や教育現場から多く聞かれるようになりました。実際に、子どもの「夜型化」はデータでも明らかになっており、保健師学校の入試でも出題されています。
今回は、保健師を目指すうえで知っておきたい「子どもの夜型化」について、小論文試験での対策も含めてまとめていきます。
| ●日本の子どもの現状 |
文部科学省の調査によると、日本の子どもの平均睡眠時間は年々短くなってきています。小学生であっても、平均で8時間前後、中学生ではさらに減少傾向にあります。これは、1980年代のデータと比較すると約1時間ほど短くなっているといわれています。
また、OECD(経済協力開発機構)諸国と比べても、日本の子どもたちは“世界で最も寝ていない国”と指摘されることもあります。特に都市部では塾や習い事により帰宅時間が遅くなり、さらにスマホやゲームの影響で寝るのが遅くなる傾向が強まっているのが実情です。
| ●夜型化している原因 |
子どもの夜型化にはさまざまな要因が絡んでいます。代表的なのは以下のとおりです。
・スマートフォンやゲームなどのメディア使用
ブルーライトによって睡眠ホルモンのメラトニン分泌が抑制され、寝つきが悪くなります。
・塾や習い事などの多忙な生活スケジュール
帰宅が遅くなり、夕食・お風呂・宿題などが後ろ倒しに。
・家庭の生活リズムそのものが夜型に寄っている
共働き家庭の増加などにより、家族全体の生活時間が遅くなる傾向も。
・SNSなどの刺激による脳の興奮状態
気持ちのオンオフが切り替えられず、布団に入っても眠れない子が増えています。
これらが複合的に絡み合い、子どもの夜型化を助長しています。
| ●夜型化を防ぐ方法 |
夜型化の対策として大切なのは、家庭や学校、地域全体での「生活習慣改善の意識」です。
・スマホやゲームの利用時間を決める
・就寝前のルーティン(読書・照明を暗めにするなど)を整える
・保護者への啓発・支援(保健師の役割!)
・学校や地域との連携で「子どもの眠り」を守る活動を広げる
睡眠は成長ホルモンの分泌に関わるだけでなく、記憶の定着や情緒の安定にも重要です。
睡眠不足が続くことで、学習意欲や集中力が低下し、いじめや不登校の一因となるケースも報告されています。
| ●小論文を書く際のポイント |
このテーマのように、「なぜそうなっているのか」と「その解決策」の両面を問われるタイプの問題では、必ず【原因→対策→自分の考え】の構成を意識しましょう。
また、保健師として地域や家庭、学校との関わりのなかでどんな働きかけができるかまで踏み込んで書けると、より専門性の高い小論文になります。
例えば、「地域の子育て教室で生活習慣の大切さを伝える活動」や「学校保健活動で保護者に向けた睡眠指導を行う」など、具体的なアイデアを盛り込めると好印象です。
| ●まとめ |
子どもの夜型化は、単なる「夜更かし」ではなく、成長や学び、心の健康にも大きく関わる問題です。保健師を目指す受験生として、こうした身近でありながら深刻な社会課題にどう向き合うかが問われています。
小論文では、「データ」や「背景知識」を使いつつ、自分の考えや保健師としての視点をしっかり盛り込むことが大切です。日頃からニュースや資料にも目を通しておくと安心ですね!
お問い合わせ
Contact
看護予備校、准看護予備校を選ぶなら京都・大阪・滋賀・兵庫から通いやすいアルファゼミナール