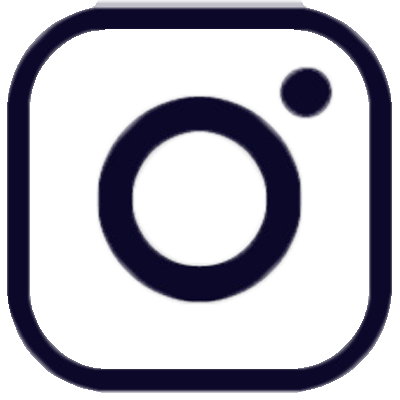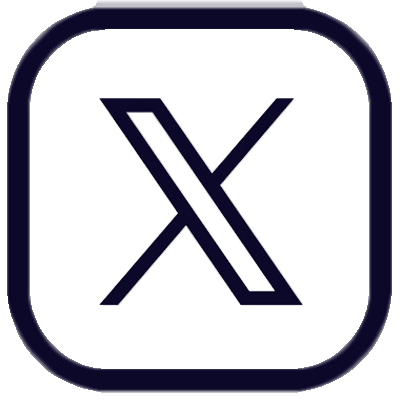お役立ち情報
2025.04.10
看護大学・看護学校の入試のグループ討論で出されたお題(7)『ことわざのカードが20枚あります。ここから一枚をひいてそれについて討論してください。』

看護大学・看護学校の入試のグループ討論で出されたお題(7)
⁻『ことわざのカードが20枚あります。ここから一枚をひいてそれについて討論してください。』
“ことわざ討論”ってどういうこと?入試での意図と対策を解説します
看護大学や看護専門学校の入試では、面接や小論文だけでなく、「グループ討論(ディスカッション)」が課されることがあります。
そのなかでも変わり種のテーマとして注目されているのが、「ことわざカードを引いて、それについて討論してください」というもの。 一見すると中学校の国語の授業のようですが、ここには“看護職としての資質”がしっかり見られています。 どんなことに気をつけるべきか、どのように話を展開すれば良いか、一緒に見ていきましょう!
| ●「ことわざ討論」ってどう進めるの? |
このタイプのグループ討論では、まず参加者のうち誰かが“ことわざカード”を1枚引きます。
そこに書かれているのは「猫に小判」「石の上にも三年」「急がば回れ」など、日常でも耳にするようなことわざ。
でも、中には普段使っていないと、意味がパッと出てこないものもあるのが正直なところですよね。
まずはそのことわざの意味を全員で確認し、それぞれの考えや経験をもとに話を広げていくのが基本的な流れです。 知らないことわざが出てしまっても、慌てなくて大丈夫。他の参加者の話をよく聞きながら、自分なりの意見を見つけていく姿勢が大切です。
たとえば「猫に小判」であれば、
「医療現場でも、高度な治療や設備があっても、患者さんがその意味を理解できていなければ本当の意味での“ケア”にはならない。伝える側の工夫や相手に合った説明の重要性を感じる」
といったように、
“ことわざ→現実の医療現場”という橋渡しができると評価が高まります。
| ●グループ討論の進め方 |
このようなディスカッションでは、ただ発言するだけではなく「いかにチームで話し合えるか」が重要な評価ポイントになります。
以下のような点を意識して臨んでみましょう。
・話し始めの人(司会役)をスムーズに決める
・ことわざの意味を簡潔に共有する
・一人ひとりの発言を丁寧に拾う・・・「今の意見、すごく共感しました」「私も似た経験があります」など
・話を広げる質問を投げかける・・・「皆さんは医療現場でこれに似た場面を想像できますか?」など
・まとまりが出てきたらまとめ役を立てる
決して声が大きい人が有利というわけではなく、「聞く力」「話をまとめる力」「協力し合う姿勢」こそが試されています。
| ●試験官は何を見ているか |
このグループ討論で面接官が見ているのは、“知識”よりも“姿勢”です。
「知らないことわざでも素直に話を聞いて学ぼうとするか」
「相手の意見に耳を傾けられるか」
「自分の体験や考えを冷静に話せるか」
そうした医療職に必要な基本的なコミュニケーション能力や協調性が見られているのです。
また、ことわざをどのように“医療や看護”の場面に結びつけて考えるかという「想像力」「応用力」も見逃せないポイント。
「石の上にも三年」なら「新人看護師として、はじめはうまくいかなくても続けることが大切」、 「急がば回れ」なら「手技においても安全性を確保することが最優先」など、実体験や理想と重ねて語れるとよいでしょう。
| ●まとめ |
「ことわざ討論」は、意外性のあるテーマでありながら、看護職としての資質をじっくり見極めることができる試験形式です。
ことわざの知識だけにこだわらず、「知らないなら素直に聞く」「人の意見を尊重する」「自分の経験をもとに意見を出す」といった柔軟な対応が何よりも大切です。
また、どんなことわざが出ても、医療現場や人との関わりにつなげて語れるよう、普段から「自分だったらどう考えるか?」を意識しておくと安心です。 緊張せず、誠実な姿勢で臨みましょう。あなたの“人間力”が問われている試験なのですから。
お問い合わせ
Contact
看護予備校、准看護予備校を選ぶなら京都・大阪・滋賀・兵庫から通いやすいアルファゼミナール