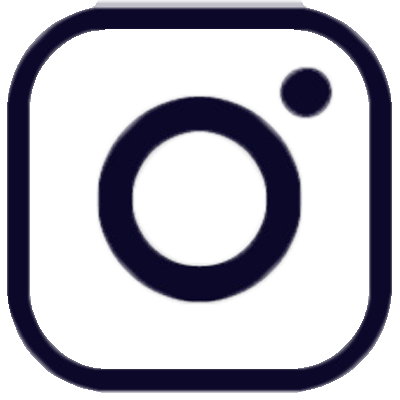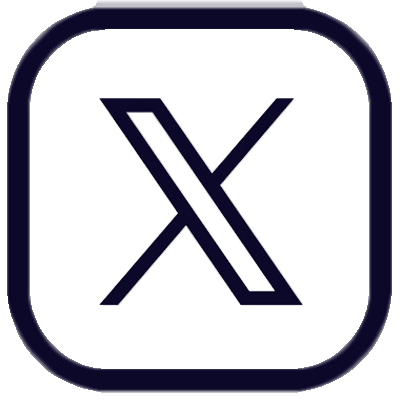お役立ち情報
2025.04.10
助産学校の入試で出た小論文のお題(6)『夫の育児参加についてあなたの考えを書きなさい(800字)』

助産学校の入試で出た小論文のお題(6)
⁻『夫の育児参加についてあなたの考えることを書きなさい(800字)』
夫の育児参加──小論文で問われる現代の家族のかたちとは?
「夫の育児参加」は、助産学校の入試で近年よく出題されるテーマのひとつです。 少子化が進む一方で、共働き家庭の増加や育児の価値観の多様化など、社会全体が子育てのかたちを見直す転換期にあります。
このテーマでは、制度面・職場環境・家族観といった幅広い視点から考えることが求められます。 未来の助産師として、家庭と社会のつながりをどう見つめ、支えていけるかを一緒に考えてみましょう。
| ●夫の育児参加の現状 |
厚生労働省の「令和4年度雇用均等基本調査」によると、男性の育児休業取得率は約17.13%と、過去最高を記録しました。
とはいえ、依然として女性の取得率(85.1%)とは大きな差があり、男性の取得は「特別なこと」として見られがちです。
特に中小企業や医療職など人手不足の業界では、代替要員の確保が難しく、育児休業を取りづらい現状があります。
また、「育児を理由に休むのは甘えでは?」という古い価値観が職場に根強く残っているケースもあり、取得した男性が肩身の狭い思いをすることも。
一方で、共働き世帯の増加により、子育てはもはや「母親だけの仕事」ではなくなってきています。 育児休業を取得した男性の多くは、「子どもとの絆が深まった」「家事育児に自信がついた」と答えており、本人や家族にとっても良い影響があることがわかっています。
| ●なぜこのお題が最近よく出るのか |
このテーマが頻繁に出題される背景には、「育児=女性の役割」という旧来の価値観を見直す社会の動きがあります。 政府は「健やか親子21(第2次)」などの施策を通じて、男性の育児参加を積極的に推進しています。
特に産後の母親は、体力的にも精神的にも不安定になりやすく、パートナーのサポートが不可欠です。 夫の育児参加は、産後うつの予防や育児負担の軽減、夫婦関係の安定にもつながります。 また、女性がキャリアを継続するためにも、男性側の育児参加が必要です。
「子育ては夫婦で協力して行うもの」という意識が当たり前になることで、子どもにとっても健全な家庭環境が整います。
| ●小論文を書く際のポイント |
このテーマでは、「育児は夫婦で協力して行うもの」という立場から、 制度や職場の現状、家庭のメリット、社会の変化などをバランスよく盛り込むと良いでしょう。
加えて、「助産師としてできること」を必ず入れるのがおすすめです。
たとえば…
・両親学級や育児教室での夫向けプログラムの充実
・パートナーへの声かけやケアの重要性を伝える
・地域で父親同士のつながりを作る取り組みの提案
などが考えられます。
一方で、現実的なデメリットにも目を向けましょう。 育児休暇中の職場の人員不足や、復職時のキャリアへの影響なども事実として存在します。 そうした課題をただ否定するのではなく、「どうすれば解決に向かえるか?」という視点を持つと、説得力のある文章になります。
| ●まとめ |
「夫の育児参加」というテーマは、家族のあり方、社会制度、働き方、性別の役割など、さまざまな要素が絡み合った現代的なお題です。
単に制度の話に終始するのではなく、「なぜ大切なのか」「それによって誰が救われるのか」まで深く掘り下げることが大切です。
そして、助産師は、出産や育児のスタートラインに寄り添う専門職。
夫の育児参加を後押しする存在として、社会にどんな働きかけができるのかを考えることは、あなた自身の将来にもつながるはずです。
お問い合わせ
Contact
看護予備校、准看護予備校を選ぶなら京都・大阪・滋賀・兵庫から通いやすいアルファゼミナール