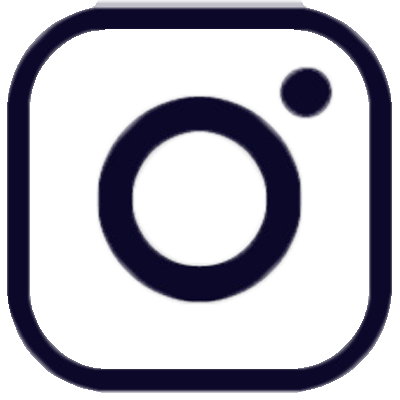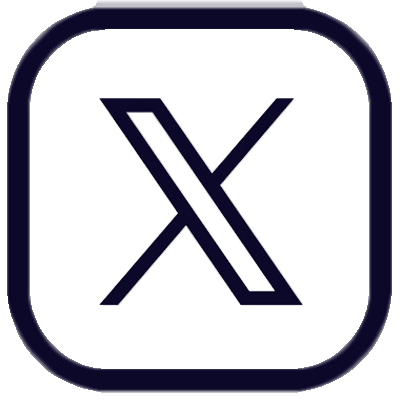お役立ち情報
2025.04.09
助産学校の入試で出た小論文のお題(4)『食育について(800字)』

助産学校の入試で出た小論文のお題(4)
⁻『食育について(800字)』
「食育って、なんだか大事そうだけど…何を書けばいいの?」
そんなふうに悩んでいる受験生も多いのではないでしょうか。
最近の助産学校の小論文では、「食育」や「子どもの健康」にまつわるテーマがよく出題されます。妊娠中・育児中の食事が赤ちゃんの健やかな成長と深く関わっているからこそ、助産師の立場から食を考える力が求められているのかもしれません。
この記事では、「食育ってなに?」「どんな視点で書けばいいの?」という疑問に答えながら、書きやすくまとめるコツも紹介していきます。あなたらしい文章が書けるよう、ぜひ参考にしてみてくださいね。
| ●食育とは |
「食育」とは、食べることの大切さを学び、心身の健康を支える正しい食習慣を身につけるための教育です。文部科学省によれば、食育は「生きる力を育む基礎」とされています。ただ栄養を摂るだけでなく、どんな食材を選ぶか、誰とどう食べるか、そして感謝の気持ちを持つことまで含まれます。
また、食育は子どもの成長だけでなく、大人にとっても重要なテーマです。とくに妊娠中や産後の女性には、食事が身体と心の安定、そして赤ちゃんの健やかな成長に直結します。助産師をめざす人にとって、食育の理解は必須の知識といえるでしょう。
| ●食育の現状と課題 |
食育は学校教育にも組み込まれ、家庭科や給食指導の中で実践されています。最近では、地産地消や産地にこだわった食材を使ったレシピの紹介、地元農家との連携など、多様な取り組みも進んでいます。食育基本法の施行(2005年)以降、国を挙げての推進が続いています。
しかし、現代社会ではインスタント食品やレトルト食品の普及により、簡便さを優先した食生活が定着しつつあります。孤食(ひとりで食事をとること)や、朝食欠食の問題も深刻で、若年層の健康や情緒面への影響が懸念されています。 文部科学省の調査では、朝食を食べる子どもほど集中力や学力が高い傾向があるとされています。朝食の大切さを広める啓発活動も進んでいますが、まだ十分とは言えません。
また、妊産婦への食事指導の現場でも、つわりによる食欲不振や体重管理の難しさに直面することがあります。助産師は、食べやすい食品や少量でも栄養のある食べ物の提案を通して、妊婦に寄り添う支援が求められます。
| ●結論の出にくいお題のまとめ方 |
「食育」のように答えが一つに決まらないテーマでは、「何を大切にしたいか」という自分の視点を明確にすることがポイントです。
たとえば「健康を守るための基礎としての食育が大切」という立場をとるなら、その理由と具体例(例:朝食と集中力の関係、妊婦への食事支援)を筋道立てて書きます。そして最後には、「助産師としてどう活かしたいか」「子どもの未来を支える力として、家庭や地域と協力していきたい」など、自分の思いにつなげましょう。
| ●まとめ |
食育は、単なる知識の伝達ではなく、生きる力を育む大切な営みです。食べることの楽しさ、栄養バランス、感謝の気持ち
——これらを伝えていくことで、子どもたちの健康や心の成長を支えることができます。
助産師という仕事においても、妊産婦への食事指導や育児支援の中で、食育の考え方は大きな力となるでしょう。自分自身の生活にも取り入れながら、未来の家族や社会に貢献できる視点を小論文でも表現してみてください。
お問い合わせ
Contact
看護予備校、准看護予備校を選ぶなら京都・大阪・滋賀・兵庫から通いやすいアルファゼミナール