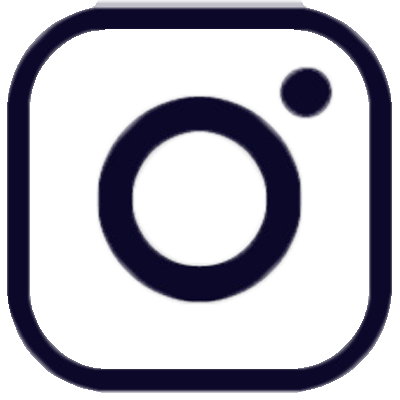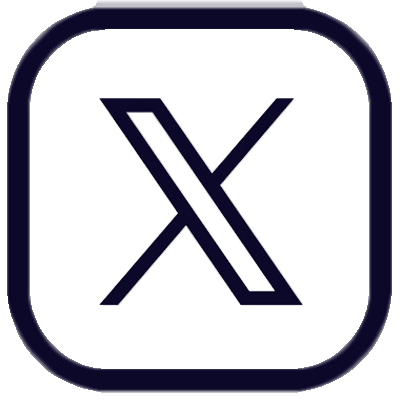お役立ち情報
2025.04.08
保健師学校の入試で出た小論文のお題(3)『改善の見込みのない患者に対し、病院としては急性患者のためにベッドを空けたいので施設へ移したいが、患者は納得しているわけではなく、ケアも必要である。あなたはどんな支援ができるか(時間50分)』

保健師学校の入試で出た小論文のお題(3)
⁻『改善の見込みのない患者に対し、病院としては急性患者のためにベッドを空けたいので施設へ移したいが、患者は納得しているわけではなく、ケアも必要である。あなたはどんな支援ができるか(時間50分)』
近年、日本の医療現場では病床数の逼迫が深刻な課題となっています。厚生労働省の「令和5年医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況」によれば、2023年時点での病床利用率や平均在院日数が報告されています 。
このような状況の中、改善の見込みが少ない患者さんに対して、病院側が急性期患者の受け入れのためにベッドを空ける必要性から、施設への転院を検討するケースが増えています。しかし、患者さん自身が転院に納得していない場合や、引き続き手厚いケアが必要な場合、どのような支援が求められるのでしょうか。
| ●現状と問題点 |
日本の平均在院日数は他国と比較して長い傾向があります。例えば、2022年のデータでは、日本の平均在院日数は27.3日と報告されています 。この長期入院の背景には、高齢化社会の進行や慢性疾患の増加が影響しています。(※1)
一方で、急性期患者の受け入れを円滑に行うためには、病床の適切な運用が不可欠です。しかし、改善の見込みが少ない患者さんに対する転院の提案は、患者さんやご家族の心理的負担を増加させる可能性があります。
| ●小論文を書く際のポイント |
このテーマに取り組む際、以下の点を考慮すると良いでしょう:
・患者さんの意思の尊重:患者さんが転院に対してどのような思いを持っているのかを丁寧に傾聴し、その意思を尊重する姿勢が重要です。
・多職種連携の推進:医師、看護師、ソーシャルワーカーなど、多職種が連携して患者さんやご家族に対する説明やサポートを行うことで、信頼関係を築くことができます。
・地域資源の活用:転院先の施設や在宅医療の選択肢について、地域の医療資源を把握し、患者さんに最適なケアプランを提案することが求められます。
・倫理的視点の考慮:患者さんの自己決定権やQOL(生活の質)を重視し、医療者としての倫理観を持って対応することが不可欠です。
| ●書きづらい人へのアドバイス |
このテーマは複雑で書きづらいと感じるかもしれません。以下のアプローチを試してみてください:
・具体的な事例を想定する:
架空のケースを設定し、その患者さんに対してどのような支援が考えられるかを検討すると、具体的な内容が浮かびやすくなります。
・自分の価値観を振り返る:
医療者として、患者さんの意思や権利をどのように尊重すべきか、自身の考えを整理することで、論旨が明確になります。
| ●まとめ |
病床の逼迫という現実的な課題と、患者さんの意思やケアの必要性とのバランスを取ることは、医療現場における重要なテーマです。保健師として、患者さん一人ひとりの状況を丁寧に把握し、多職種と連携しながら最適な支援を提供する姿勢が求められます。
(※1)厚生労働省 令和5(2023)年医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況 ![]()
お問い合わせ
Contact
看護予備校、准看護予備校を選ぶなら京都・大阪・滋賀・兵庫から通いやすいアルファゼミナール