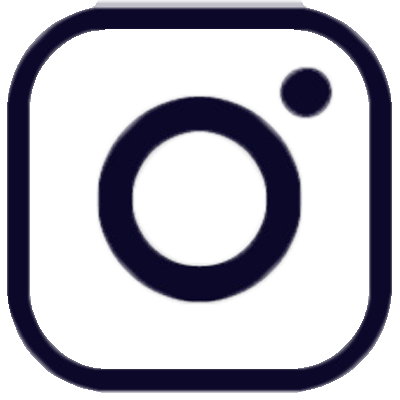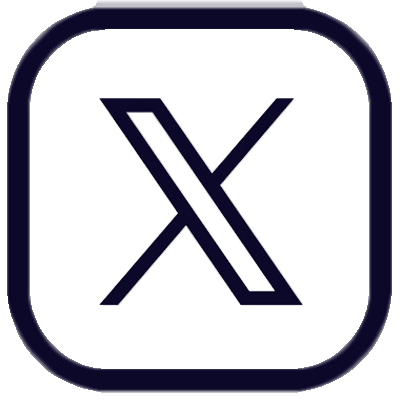お役立ち情報
2025.04.07
看護学校の入試で出た小論文・作文のお題(6)『日本の女性が世界一寿命が長いことについて(400字・時間50分)』

看護学校の入試で出た小論文・作文のお題(6)
⁻『日本の女性が世界一寿命が長いことについて(400字・時間50分)』
「日本の女性が世界一寿命が長いのはなぜ?」
この問いは、単なる事実確認ではなく、背景にある社会や生活習慣、医療制度、そして今後の課題にまで目を向けて考える力を問うものです。小論文試験でこのテーマが出題された背景には、保健・医療・福祉の分野に進もうとする受験生が、健康や高齢社会についての関心と理解を持っているかを見たいという意図があります。
「長生き」=「幸せ」ではありません。「健康で」「生きがいをもって」長生きするには何が大切か。この機会にぜひ、自分の考えを深めてみましょう。
| ●日本人の平均寿命について |
日本人の平均寿命は年々延びており、2023年時点で女性は87.1歳、男性は81.05歳と世界でもトップクラスの長寿国です(厚生労働省・簡易生命表より)。とくに日本の女性の寿命は世界一であり、長寿大国と呼ばれています。世界と比べても、日本の女性はスイスやシンガポールなどを上回る水準にあります(参考:ELEMINIST「長寿国ランキング2023」)。
この背景には、以下のような複合的な要因があると考えられます。
・医療制度が整っている
・健康意識が高い(定期健診、減塩文化など)
・和食中心の食生活(魚や野菜、発酵食品が多い)
・女性ホルモン(エストロゲン)による心血管保護効果
・社会的つながりや家族との関係性の維持
また、日本には「長生き遺伝子(FOXO3遺伝子)」を持つ人が多いという研究もあり、遺伝的な要因も一定の影響を及ぼしているとされています。
| ●小論文を書く際のポイント |
小論文では、ただデータを並べるのではなく、「なぜ長寿なのか」だけでなく、「それが今後の社会にとってどういう意味を持つのか」まで考察できると深みが出ます。
・健康寿命との違いに注目しよう
平均寿命は延びていますが、「健康寿命」(日常生活を制限されずに過ごせる期間)は、女性で75.38歳、男性で72.68歳(2022年・厚労省調査)と、平均寿命との差が約10年あります。この差の期間、要介護状態や寝たきりになってしまう高齢者も多く、医療や介護サービスの負担が増す原因にもなっています。
このギャップこそ、日本社会が抱える今後の課題です。
・長寿社会のメリットと課題を整理しよう
メリットとしては、経験豊富な高齢者が地域社会に貢献できることなどが挙げられます。一方で、医療費や介護人材の不足、独居高齢者の増加など、支える側の負担も大きくなります。
・「健康で長生きする」にはどうすれば?
地域医療や予防医療の充実、バランスの良い食生活、運動習慣、そして社会的つながり(孤独の防止)などが重要です。とくに「生きがい」や「役割のある暮らし」は、健康寿命を延ばす鍵です。
| ●まとめ |
日本の女性が長寿である背景には、医療・食事・遺伝・社会的な習慣など様々な要因が絡んでいます。しかし今後の高齢化社会では、「長く生きる」こと以上に「どのように生きるか」が問われる時代になります。受験生としては、数字や事実だけでなく、その背景やこれからの課題、自分が医療職としてどう関わっていけるかまで踏み込んで考えてみてください。
患者さんや地域の人々の“人生そのもの”に寄り添う看護師・保健師になるために、小さな問いから社会を見つめる視点を持ちましょう。
お問い合わせ
Contact
看護予備校、准看護予備校を選ぶなら京都・大阪・滋賀・兵庫から通いやすいアルファゼミナール