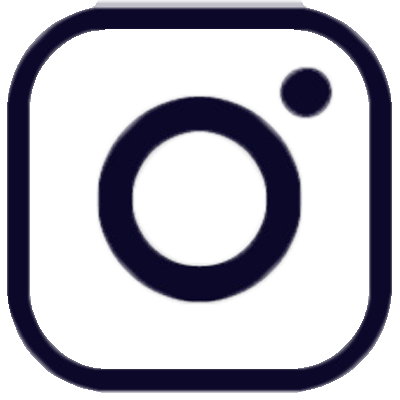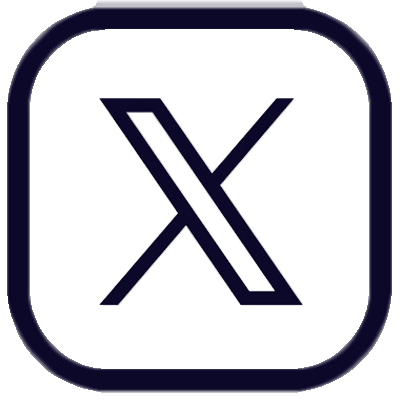お役立ち情報
2025.04.07
保健師学校の入試で出た小論文のお題(2)『日本のクルマ社会における高齢者の運転について』

保健師学校の入試で出た小論文のお題(2)
⁻『日本のクルマ社会における高齢者の運転について』
日本の高齢化が進む中、高齢者の運転に関する問題が社会的な関心を集めています。特に地方では、車が生活の必需品となっており、高齢者の運転継続や免許返納に関する議論が活発です。
本記事では、高齢者の運転に関する現状と課題、そしてその対策について考察します。
| ●高齢者運転の現状 |
近年、日本における交通事故全体の件数は減少傾向にありますが、75歳以上の高齢運転者による死亡事故件数は横ばいで推移しています。その結果、全体の死亡事故件数に占める75歳以上の運転者による事故の割合は増加傾向にあります 。
高齢者の運転に関しては、運動機能の低下、反射・反応速度の鈍化、視力や認知機能の衰えなどが事故の要因として挙げられます。
特にアクセルとブレーキの踏み間違いによる事故が社会問題となっています。
| ●小論文を書く際のポイント |
高齢者の運転に関する小論文を書く際には、以下のポイントを考慮すると良いでしょう。
-
地方と都市部での車の必要性の違い:
地方では公共交通機関が限られており、車が生活必需品となっています。一方、都市部では公共交通が発達しており、車なしでも生活が可能です。この違いを踏まえて、高齢者の免許返納の難しさや必要性を論じることが重要です。 -
免許返納の現状と課題:
高齢者の免許返納は進んでいるものの、地域差があります。特に地方では、免許返納後の移動手段の確保が課題となっています。自治体によるコミュニティバスの運行やタクシーチケットの配布などの取り組みも行われていますが、十分とは言えません 。(※1) -
自動運転技術の進展:
自動運転技術はレベル0からレベル5までの段階があります。現在、レベル2(運転支援)の車両が市販されており、レベル3(条件付き自動運転)の実用化も進んでいます 。将来的には高齢者の移動手段として期待されていますが、普及には時間がかかると考えられます。(※2) -
医療・福祉の観点からの支援:
訪問看護や移動診療など、医療サービスの提供方法も多様化しています。しかし、これらのサービスが高齢者の移動手段の代替となるには、さらなる拡充が必要です。
| ●まとめ |
高齢者の運転に関する問題は、単なる個人の問題ではなく、社会全体で取り組むべき課題です。地方と都市部での状況の違い、免許返納後の生活支援、自動運転技術の進展、医療・福祉サービスの充実など、多角的な視点からのアプローチが求められます。小論文を作成する際には、これらの要素をバランスよく盛り込み、具体的なデータや事例を用いて論じることで、説得力のある内容となるでしょう。
(※1)内閣府 令和6年版交通安全白書 ![]()
(※2)日本損害保険協会 自動運転はいま ![]()
お問い合わせ
Contact
看護予備校、准看護予備校を選ぶなら京都・大阪・滋賀・兵庫から通いやすいアルファゼミナール