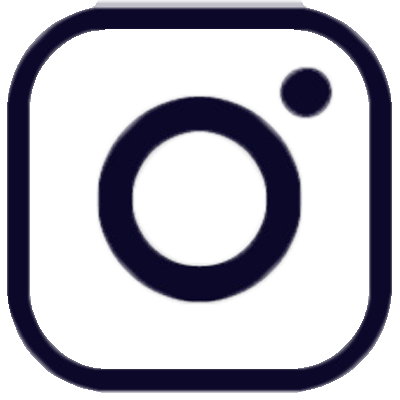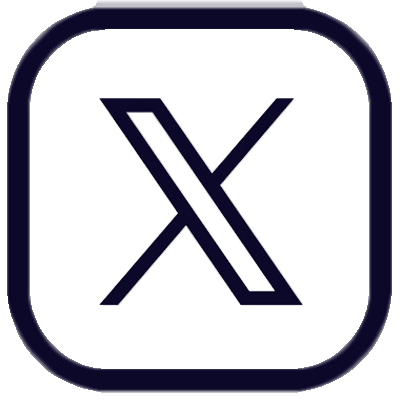お役立ち情報
2025.04.04
看護学校の入試で出た小論文・作文のお題(4)『中学生が読書をしないことについて、あなたの考えを書きなさい。(時間30分)』

看護学校の入試で出た小論文・作文のお題(4)
⁻『中学生が読書をしないことについて、あなたの考えを書きなさい。(時間30分)』
看護学校や看護大学の入試では、医療・福祉に関する話題だけでなく、社会の動きや教育、文化に関するテーマが出題されることもあります。今回取り上げるのは「中学生が読書をしないこと」についての小論文テーマ。これは、受験生の社会的関心の広さや、課題への考察力を試すためのものです。
以下では、受験対策としての考え方のヒントを「中学生の読書離れの現状」と「書き方のポイント」から解説していきます。
| ●中学生の読書時間減少の現状 |
文部科学省の「全国学力・学習状況調査」などによれば、中学生の1日の平均読書時間は年々減少傾向にあります。特に平日の読書時間が「0分」と答える中学生の割合は、20年前と比べて明らかに増加しています。一方で、大人の読書時間も減少しており、文化庁の調査によると「1カ月に1冊も本を読まない」人の割合は約半数に達しています。
読書離れの背景にはいくつかの要因が挙げられます。まず、スマートフォンやゲーム機の普及により、スキマ時間がデジタルコンテンツに取って代わられていること。また、塾や習い事、部活動などによって自由時間が少なくなっている現状も一因です。さらには、家庭内や地域で読書に触れる機会そのものが減っていることも見逃せません。
加えて、町の書店が減少していることも子どもの読書離れに拍車をかけています。気軽に立ち寄れる本屋が少なくなり、「本との出会い」の機会が失われつつあるのです。
一方で、テレビを見る時間も減少傾向にあり、以前はテレビから得られていた言葉や知識すら補えないまま、情報が断片的にスマホから流れてくるだけの時代になっています。こうした状況が続くと、子どもたちの語彙力や読解力の低下、さらには集中力の欠如といった課題が生まれてきます。
看護の現場でも、患者さんの言葉の真意をくみ取る力、文章や記録の正確な読み取り力が求められるため、国語力の低下は無関係ではありません。
| ●小論文を書く際のポイント |
このテーマで小論文を書く際には、まず「現状を事実に基づいて示す」ことが大切です。データを簡潔に盛り込むことで説得力が増します。そして、原因を一面的に見るのではなく、複数の視点から考察しましょう。スマホだけが原因なのか、家庭や地域社会の在り方にも問題はないかなど、広く考えることが求められます。
次に、自分自身の経験を交えると、文章に説得力と親しみが生まれます。たとえば、「私も中学生の頃は読書が苦手だったが、ある本との出会いで考えが変わった」といったエピソードを短く入れると、より印象的になります。
最後に、「ではどうすればいいのか?」という提案で文章を締めくくりましょう。「家庭で読書時間を設ける」「学校図書館を活性化させる」「SNSで読書感想をシェアする文化を広める」など、具体的な対策があると良いですね。
| ●この小論文が看護受験で問うていること |
このようなテーマを通して、入試で問われているのは「一つの社会問題を多角的にとらえ、自分の言葉で論理的に表現する力」です。看護師には、患者さんの生活背景や価値観を理解し、柔軟に対応する力が求められます。つまり、このテーマは、単なる文化的な話題にとどまらず、受験生の思考の深さや視野の広さを測るためのものなのです。
| ●まとめ |
中学生の読書離れは、家庭や社会全体の影響を受けて生まれた複合的な課題です。しかし、工夫次第で本に親しむきっかけを増やすことは可能です。
小論文では、問題提起から原因の考察、そして自分なりの解決策まで、論理的に構成することが大切です。日頃からニュースや教育に関する話題に触れて、自分の考えを持つようにしておくと、こうしたテーマにも落ち着いて対応できるようになります。
フィード
ブログ内検索
お問い合わせ
Contact
看護予備校、准看護予備校を選ぶなら京都・大阪・滋賀・兵庫から通いやすいアルファゼミナール